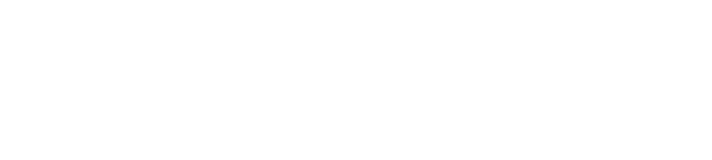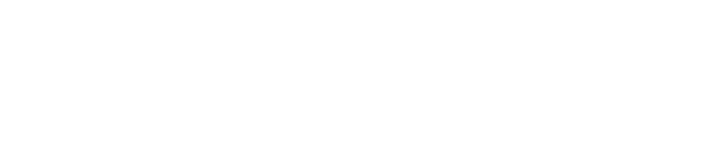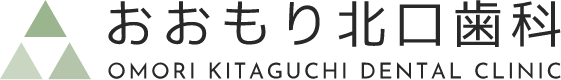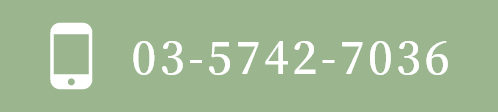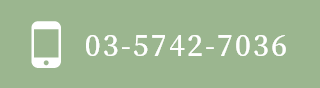歯並びが悪いことで起こる影響とは?見た目だけじゃない、隠れた健康問題
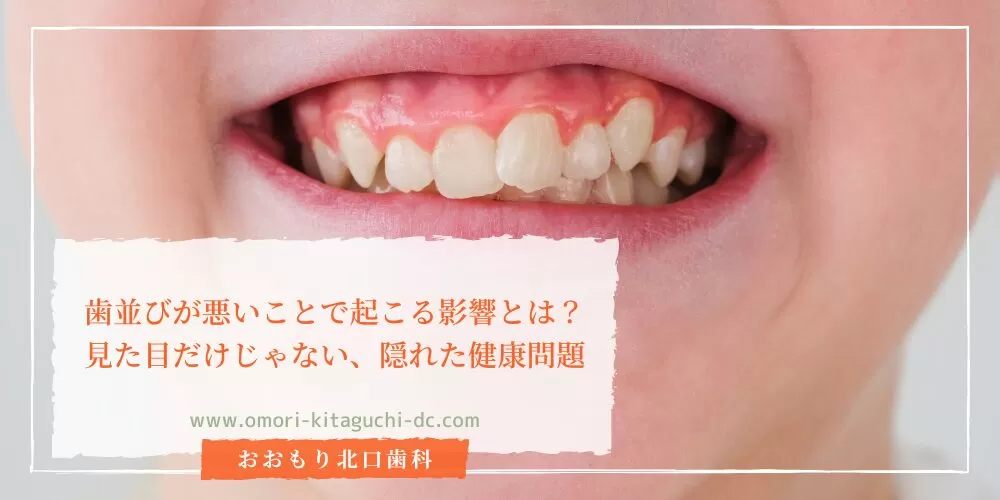
東京都大森駅徒歩50秒の歯医者・歯科「おおもり北口歯科」です。
歯並びの乱れは、見た目の印象だけでなく、実は全身の健康にも深く関わっています。多くの人が歯並びの悪さを審美的な問題として捉えがちですが、放置することで虫歯や歯周病のリスクを高めるだけでなく、消化器系のトラブル、頭痛、肩こりといった一見無関係に見える様々な体調不良を引き起こす可能性があります。さらに、お子様の場合は顎の成長に影響を及ぼしたり、大人の方でも精神的なストレスの一因になったりすることもあります。
この記事では、歯並びの悪さがもたらす具体的な健康問題、代表的な不正咬合の種類、そして歯並びが悪くなる主な原因について詳しく解説します。そして、これらの問題が矯正治療によってどのように改善できるのか、その方法や治療の流れについてもご紹介します。ご自身の歯並びが健康にどのような影響を与えているのか、また、どのような改善策があるのかを知るきっかけにしていただければ幸いです。
歯並びは見た目だけの問題?放置するリスクとは
歯並びの問題を、単なる見た目の悩みや、笑顔に自信が持てないといった審美的な側面に限って捉えている方は少なくありません。もちろん、美しい歯並びは自信につながり、社会生活においても良い影響を与えることは確かです。しかし、歯並びの乱れはそれだけに留まらず、私たちの全身の健康にまで多岐にわたる悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、歯が不規則に並んでいると、食べ物が挟まりやすくなったり、歯ブラシが届きにくくなったりすることで、虫歯や歯周病のリスクが格段に高まります。また、噛み合わせが悪いと、食べ物を効率的に咀嚼できず、胃腸への負担が増大することもあります。さらに、顎の位置がずれることで、頭痛や肩こり、めまいといった不定愁訴を引き起こすケースも報告されています。
このように、歯並びの悪さを放置することは、口腔内だけでなく、身体全体の健康バランスを崩す原因となりえます。これからご紹介する具体的な健康問題を通じて、歯並びが全身に与える影響について深く理解し、ご自身の歯並びの状態を見つめ直すきっかけにしていただければと思います。
【影響別】歯並びが悪いことで起こる健康上の問題
このセクションでは、歯並びの悪さが引き起こす具体的な健康問題を一つひとつ詳しく解説していきます。虫歯や歯周病、口臭、消化不良、全身の不調、顎関節症、発音のしづらさ、さらには精神的な影響まで、多岐にわたる問題を取り上げますので、ご自身の悩みに照らし合わせながら読み進めてみてください。
虫歯や歯周病のリスクが高まる
歯並びが悪いと、歯が重なり合っていたり、不自然な隙間ができていたりする場所が多くなります。このような部位は歯ブラシの毛先が届きにくく、食べかすやプラーク(歯垢)が溜まりやすい環境です。結果として、虫歯菌や歯周病菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが格段に高まってしまいます。
どれほど丁寧に歯磨きをしていても、デコボコした歯並びの隅々まで清潔に保つことは非常に困難です。セルフケアだけでは限界があり、毎日の歯磨きを欠かさず行っていても、細菌の温床となってしまう可能性は避けられません。健康な歯を長く保つためにも、歯並びの改善は重要です。
口臭の原因になる(口呼吸・清掃不良)
歯並びの悪さが口臭の原因となるケースは少なくありません。主な原因は、「清掃不良」と「口呼吸」の2つが挙げられます。まず「清掃不良」ですが、歯並びが乱れていると歯と歯の間や重なり合った部分に食べかすやプラークが残りやすくなります。これらが腐敗することで、不快な臭いを発するガスが発生し、口臭となります。
次に「口呼吸」ですが、出っ歯などで唇が閉じにくい歯並びの場合、口が常に開いた状態になりがちです。これにより口腔内が乾燥し、唾液の分泌量が減少してしまいます。唾液には口腔内の汚れを洗い流したり、殺菌作用によって細菌の増殖を抑えたりする働きがあります。唾液の自浄作用が低下すると、細菌が繁殖しやすくなり、これが口臭の大きな原因となるのです。
消化不良など胃腸への負担
噛み合わせが悪いと、食べ物を十分に細かく噛み砕くことができません。本来であれば、歯で食べ物を効率よくすりつぶすことで、胃や腸での消化負担を軽減できるのですが、歯並びが乱れていると、この咀嚼(そしゃく)機能が十分に働かなくなります。その結果、大きな塊のまま食べ物が胃に送られてしまうため、消化に余分な時間とエネルギーがかかり、胃腸に大きな負担をかけてしまいます。
消化不良が慢性化すると、胃もたれや腹部の不快感だけでなく、栄養の吸収効率が低下することも考えられます。全身の健康は消化器系の状態に大きく左右されるため、噛み合わせの問題は、口の中だけでなく、消化器系全体の健康にも影響を及ぼす可能性があるのです。
全身の不調(頭痛・肩こり)につながる
歯並びや噛み合わせのズレは、頭痛や肩こりといった全身の不調の原因となることがあります。噛み合わせが悪いと、食事や会話のたびに顎の関節やその周辺の筋肉に不均衡な力がかかり、常に緊張した状態が続きます。この顎周りの筋肉の緊張は、首や肩、さらには頭部へと連鎖的に広がり、筋肉の血行不良を引き起こします。
血行不良は筋肉の疲労物質の蓄積を招き、結果として慢性的な肩こりや、締め付けられるような緊張型頭痛の原因となるのです。一見すると歯とは直接関係がないように思えるこれらの症状も、実は口の中の噛み合わせの問題に起因している可能性があるため、注意が必要です。
顎関節症を引き起こす可能性
噛み合わせの悪さは、顎の関節に過度な負担をかけ、顎関節症(がくかんせつしょう)を発症させるリスクを高めます。顎関節症は、「口を開け閉めする際にカクカク、ジャリジャリと音がする」「口が大きく開けられない」「顎の関節やその周辺に痛みがある」といった様々な症状が現れる病気です。
不適切な噛み合わせは、顎の関節やその周囲の筋肉に常にアンバランスな力を与え続けます。この持続的なストレスが関節の軟骨やディスク、靭帯などに損傷を与え、顎関節症へと進行してしまうのです。顎関節症は日常生活に大きな支障をきたす深刻な問題であり、咀嚼や会話だけでなく、食事そのものを苦痛に感じるようになることもあります。
発音・滑舌が悪くなる
歯並びが悪いと、特定の音を正しく発音することが難しくなり、滑舌が悪くなることがあります。これは、歯と歯の間に隙間があると、そこから息が漏れてしまい、正しい発音に必要な空気の流れが作れないためです。また、舌の動きが歯の位置によって制限されることも、発音に影響を与えます。
特に「サ行」や「タ行」、「ラ行」など、舌先を歯や口蓋に接触させて発音する音は、歯並びの乱れによって影響を受けやすい傾向があります。例えば、すきっ歯の場合、「サ行」が「シャ行」のように聞こえたり、舌足らずな印象を与えたりすることがあります。このような発音の困難さは、コミュニケーションにおけるコンプレックスの原因となり、自信の低下にもつながる可能性があります。
顔の歪みやコンプレックスなど精神的な影響
歯並びの問題は、見た目に大きく影響し、それが精神的なストレスやコンプレックスへとつながることが少なくありません。噛み合わせのズレは、顔の筋肉のバランスにも影響を与え、顎の骨格や筋肉の付き方に偏りをもたらすことで、顔の歪みにつながる可能性もあります。
見た目へのコンプレックスは、「人前で自然に笑えない」「口元を手で隠してしまう」といった行動に現れ、自己肯定感の低下や内向的な性格につながることもあります。特に、学生時代や就職活動など、人とのコミュニケーションが重要になる場面では、この問題がより深刻になることも考えられます。歯並びを改善することは、口元の健康だけでなく、自信を取り戻し、より明るく前向きな生活を送るための一助となるでしょう。
あなたはどのタイプ?不正咬合の主な種類
歯並びの乱れは、その形状や噛み合わせ方によって様々なタイプに分類されます。これらは「不正咬合」と呼ばれ、それぞれに異なる特徴と、引き起こしやすい健康上の問題があります。ご自身の歯並びがどのタイプに当てはまるのかを知ることは、適切な対処法や矯正治療を検討する上で重要な第一歩となります。
叢生(そうせい)
叢生(そうせい)とは、歯が顎のスペースに収まりきらず、互いに重なり合ってガタガタに生えている状態を指します。よく見られる「八重歯」も、この叢生の一種です。歯が不規則に並んでいるため、見た目に影響を与えるだけでなく、機能面でも様々な問題を引き起こします。
叢生の場合、歯と歯の間に汚れが溜まりやすく、歯ブラシの毛先が届きにくいため、毎日の丁寧な歯磨きでも磨き残しが生じやすいという特徴があります。これにより、虫歯や歯周病のリスクが非常に高まります。清掃性の悪さは、口腔内の健康維持にとって大きなデメリットとなり、将来的な歯の喪失にもつながりかねません。
上顎前突(じょうがくぜんとつ)|出っ歯
上顎前突(じょうがくぜんとつ)は、一般的に「出っ歯」と呼ばれる状態です。上の前歯が下の前歯よりも大きく前に突き出ており、噛み合わせたときに上下の歯が適切に噛み合わない状態を指します。見た目の印象に大きく関わるだけでなく、口腔機能にも影響を与えることがあります。
出っ歯の方は、口を完全に閉じにくい傾向があり、口呼吸になりやすいという問題があります。口呼吸は、口腔内の乾燥を引き起こし、虫歯や歯周病、口臭の原因となることがあります。また、転倒した際に上の前歯をぶつけやすく、歯が欠けたり折れたりするリスクが高まります。遺伝的な要因のほか、幼少期の指しゃぶりや爪噛みといった癖が原因となる場合もあります。
下顎前突(かがくぜんとつ)|受け口
下顎前突(かがくぜんとつ)は「受け口」とも呼ばれ、下の歯が上の歯よりも前に出ている噛み合わせの状態を指します。これは、下の顎が過度に成長している場合や、上の顎の発育が不十分な場合など、骨格的な問題が原因となっていることが多いです。
受け口の場合、前歯で食べ物を噛み切ることが難しく、咀嚼(そしゃく)機能に問題が生じることがあります。また、「サ行」や「タ行」など、特定の音が発音しにくくなる「構音障害」を引き起こすこともあります。重度の場合は、外科手術を併用した矯正治療が必要になることもあり、専門医による詳細な診断が不可欠です。
開咬(かいこう)
開咬(かいこう)は「オープンバイト」とも呼ばれ、奥歯をしっかりと噛み合わせたときに、上下の前歯が噛み合わずに隙間ができてしまう状態を指します。前歯が接しないため、食べ物をうまく噛み切ることができないという機能的な問題が顕著に現れます。
開咬の方は、前歯で食べ物を噛み切れないために奥歯に過度な負担がかかりやすく、奥歯の磨耗や痛みにつながることがあります。また、口が閉じにくいため口呼吸になりやすく、口腔乾燥による虫歯や歯周病、口臭のリスクも高まります。さらに、前歯の隙間から息が漏れてしまい、特定の音の発音が不明瞭になることもあります。
過蓋咬合(かがいこうごう)
過蓋咬合(かがいこうごう)は「ディープバイト」とも呼ばれ、噛み合わせが深すぎる状態を指します。具体的には、上の前歯が下の前歯を覆い隠してしまうほど深く噛み込んでいる状態です。一見すると歯並びが良いように見えることもありますが、様々な機能的な問題を引き起こす可能性があります。
このタイプの噛み合わせでは、下の前歯の先端が上の歯茎に常に接触したり、噛み込んだ際に上の歯茎を傷つけたりして、炎症や痛みを引き起こすことがあります。また、顎関節に過度な負担がかかりやすく、顎関節症を発症するリスクが高まります。顎の痛みや口の開閉時の違和感、カクカクといった異音など、顎関節症の症状が現れることがあります。
空隙歯列(くうげきしれつ)|すきっ歯
空隙歯列(くうげきしれつ)は、一般的に「すきっ歯」として知られています。これは、歯と歯の間に不自然な隙間が空いている状態を指します。特に前歯に隙間があると、見た目に影響を与えるだけでなく、いくつかの機能的な問題も伴います。
すきっ歯の場合、隙間から息が漏れてしまうため、「サ行」や「タ行」など、特定の音が発音しにくくなることがあります。また、食べ物が歯と歯の隙間に挟まりやすく、これが虫歯や歯周病のリスクを高める原因となります。顎の大きさと歯の大きさのバランスが悪く、顎のスペースに比べて歯が小さい場合や、舌で歯を押す癖などが原因で発生することが多いです。
なぜ歯並びは悪くなるのか?主な原因
歯並びが悪くなる原因は一つだけではなく、生まれつきの要因と、生まれてからの生活習慣や環境が複雑に絡み合っています。ご自身の歯並びや、お子さまの歯並びがなぜ悪くなってしまったのか、その原因を理解することで、将来的な歯並びの悪化予防や、適切な対処法を検討するきっかけになるでしょう。
遺伝的な要因
歯並びの乱れには、ご両親からの遺伝が大きく関わっている場合があります。例えば、顎の骨の大きさや形、歯の大きさ、歯の数といった要素は遺伝する傾向があります。顎の骨が小さいのに歯が大きい場合、歯が顎のスペースに収まりきらず、ガタガタと重なり合って生える「叢生(そうせい)」の原因となることがあります。
しかし、遺伝的要因が全てではありません。歯並びの悪さは、生まれつきの要素だけでなく、日頃の生活習慣や口腔環境によっても大きく左右されます。次の項目で解説する後天的な要因も、歯並びに影響を与える重要な要素です。
幼少期の癖(指しゃぶり、口呼吸、舌癖など)
幼少期の無意識な癖は、成長過程にある顎の骨や歯に持続的な力を加え、歯並びや顎の正常な発達を阻害することがあります。例えば、長期間にわたる「指しゃぶり」は、前歯が前に突き出す「出っ歯(上顎前突)」や、奥歯を噛み合わせたときに前歯が噛み合わない「開咬(かいこう)」の原因となることがあります。
また、「口呼吸」の癖がある場合、口周りの筋肉のバランスが崩れ、顎の成長が不十分になることがあります。これにより、歯が並ぶスペースが不足しやすくなったり、唾液による自浄作用が低下して虫歯や歯周病のリスクが高まったりすることもあります。「舌で前歯を押す癖」や、舌が正しい位置にない「舌癖」も、前歯に隙間ができる「すきっ歯(空隙歯列)」や開咬を引き起こす原因となることがあります。
これらの癖は、無意識のうちに行われていることが多いため、ご自身やお子さまにこのような癖がないか注意深く観察し、もし見つかった場合は、早めに改善に取り組むことが健康な歯並びの維持には非常に重要です。歯科医院では、舌のトレーニングなどによってこれらの癖を改善するサポートも行っています。
虫歯や歯周病、抜歯後の放置
虫歯や歯周病といったお口のトラブルも、歯並びを悪化させる後天的な原因となります。特に乳歯の虫歯を放置すると、乳歯が早期に失われ、その空いたスペースに隣の歯が傾き込んでくることがあります。これにより、後から生えてくる永久歯のスペースが不足し、永久歯が正しい位置に生えられずに歯並びが乱れる原因となります。
大人の場合でも、重度の歯周病によって歯を支える骨が失われると、歯がグラグラしたり、位置が移動したりして歯並びが悪化することがあります。また、虫歯などで歯を抜いた後に、そのスペースを放置してしまうと、残った歯が空いたスペースに傾いてきたり、噛み合う歯が伸び出してきたりして、全体の噛み合わせが崩れてしまうリスクがあります。口腔内の健康管理は、歯並びの維持にとっても非常に重要であり、定期的な歯科検診や適切な治療が歯並びを守る上で欠かせません。
歯並びは改善できる!主な矯正治療の種類と流れ
これまで歯並びの悪さが引き起こす様々な健康問題について解説してきましたが、こうした問題は歯科矯正治療によって改善が可能です。歯並びを整えることは、見た目の改善はもちろんのこと、虫歯や歯周病のリスク軽減、咀嚼機能の向上、全身の健康維持にもつながります。このセクションでは、大人になってからでも矯正治療が可能であること、どのような治療法があるのか、そして治療にかかる期間や治療後のケアについて、具体的な情報を詳しくご紹介いたします。
大人になってからでも矯正治療は可能
歯列矯正は「子どもがするもので、大人になってからではもう手遅れ」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、矯正治療は成長期の子どもだけでなく、大人になってからでも十分に可能です。歯と歯茎が健康な状態であれば、年齢に関係なく矯正治療を始めることができます。
大人の矯正治療には、ご自身の意思で治療の必要性を理解し、積極的に取り組めるという大きなメリットがあります。これまでご紹介したような虫歯や歯周病のリスク、顎関節症、発音の悩み、顔の歪みといった健康上の問題を解消できるだけでなく、コンプレックスを克服し、自信を持って笑顔になれるようになります。年齢を理由に歯並びの悩みを諦める必要は一切ありません。
主な矯正装置の種類と特徴
現代の歯列矯正治療には、様々な種類の装置があり、患者様のライフスタイルや歯並びの状態に合わせて最適な選択が可能です。それぞれの装置にはメリットとデメリットがあり、治療期間や費用、見た目の問題などを考慮して選ぶことが重要になります。ここでは、代表的な矯正方法である「ワイヤー矯正」と「マウスピース矯正」について詳しくご紹介し、それぞれの特徴や向いているケースについて解説いたします。
ワイヤー矯正(表側矯正・裏側矯正)
ワイヤー矯正は、歯の表面に「ブラケット」という小さな装置を取り付け、そこに金属のワイヤーを通して少しずつ歯を動かしていく、最も伝統的で確実な矯正方法です。ワイヤーが歯に持続的な力を加えることで、計画通りに歯を移動させることができます。
ワイヤー矯正には、歯の表面にブラケットを装着する「表側矯正」と、歯の裏側に装着する「裏側矯正(舌側矯正)」の2種類があります。表側矯正は幅広い症例に対応でき、費用も比較的抑えられるメリットがありますが、装置が目立つというデメリットがあります。一方、裏側矯正は装置がほとんど見えないため、見た目を気にされる方に選ばれることが多いですが、費用が高くなる傾向があり、発音に一時的な影響が出ることがあります。ワイヤー矯正は、ほとんどすべての不正咬合に対応できる汎用性の高さが最大の強みと言えるでしょう。
マウスピース矯正
近年、審美的な需要の高まりから人気を集めているのがマウスピース矯正です。透明なプラスチック製のマウスピース型矯正装置を一定期間ごとに交換していくことで、段階的に歯を動かします。ワイヤーやブラケットを使用しないため、装置が目立たないのが特徴です。
マウスピース矯正の最大のメリットは、透明であるため装着していてもほとんど気づかれにくく、取り外しが可能な点にあります。食事や歯磨きの際に装置を外せるため、普段と変わらない食生活を送ることができ、口腔内の衛生管理も容易です。ただし、1日20時間以上の装着が必要となるため、自己管理が非常に重要になります。また、すべての不正咬合に対応できるわけではなく、複雑な症例にはワイヤー矯正の方が適している場合もあります。目立ちにくい矯正を希望し、自己管理を徹底できる方に向いている治療法と言えるでしょう。
治療期間の目安と治療後の保定
歯列矯正治療にかかる期間は、個人の歯並びの状態や選択する治療方法によって異なりますが、一般的には1年から3年程度が目安となります。治療開始前には、歯科医師が精密検査を行い、患者様一人ひとりの状況に合わせた詳細な治療計画と期間を提示してくれます。
矯正治療が終わると、きれいな歯並びになったことに安心するかもしれませんが、治療後の「保定期間」が非常に重要です。歯は元の位置に戻ろうとする性質(後戻り)があるため、動かした歯を新しい位置に定着させるために「リテーナー(保定装置)」を使用する必要があります。リテーナーを指示通りに装着しないと、せっかく整えた歯並びが元に戻ってしまう可能性があり、治療が無駄になってしまうこともあります。美しい歯並びを維持するためには、保定期間中の適切なケアが不可欠であることを覚えておきましょう。
まとめ:歯並びが気になったら、まずは専門家へ相談を
歯並びの乱れは、単に見た目の問題にとどまらず、虫歯や歯周病のリスクを高めたり、口臭、消化不良、さらには頭痛や肩こり、顎関節症といった全身の健康問題にもつながる可能性があることをお伝えしてきました。出っ歯やすきっ歯など、不正咬合にはさまざまな種類があり、それぞれが引き起こす機能的な問題も多岐にわたります。また、歯並びが悪くなる原因も、遺伝的なものから幼少期の癖、虫歯や歯周病といった後天的な要因まで、一つではありません。
しかし、ご自身の歯並びの状態が気になる場合でも、諦める必要はありません。現代の歯科矯正治療は、年齢に関わらず幅広い症例に対応できるよう進化しており、ワイヤー矯正やマウスピース矯正など、ライフスタイルに合わせた様々な治療法が選択可能です。もし、この記事を読んでご自身の歯並びや噛み合わせについて不安を感じたり、改善したいと考えたりした場合は、まずは自己判断せずに歯科医師などの専門家に相談することが大切です。専門家による正確な診断と適切なアドバイスを受けることが、健康な口元と全身の健康を取り戻すための第一歩となります。
監修者
神奈川歯科大学卒業後、中沢歯科医院 訪問歯科治療担当
医療法人社団葵実会青葉歯科医院 分院長就任
シンタニ銀座歯科口腔外科クリニック 親知らず口腔外科担当
医療法人社団和晃会クリーン歯科 分院長就任
医療法人社団横浜駅前歯科矯正歯科 矯正口腔外科担当
医療法人社団希翔会日比谷通りスクエア歯科
おおもり北口歯科 開業
昭和大学口腔外科退局後は、昭和大学歯学部学生口腔外科実習指導担当経験 また、都内、神奈川県内の各歯科医院にて出張手術担当。
【所属】
・日本口腔外科学会
・ICOI国際インプラント学会
・日本口腔インプラント学会
・顎顔面インプラント学会
・顎咬合学会
・スポーツ歯科学会
・アメリカ心臓協会AHA
・スタディーグループFTP主宰
【略歴】
・神奈川歯科大学 卒業
・中沢歯科医院 訪問歯科治療担当
・医療法人社団葵実会青葉歯科医院 分院長就任
・シンタニ銀座歯科口腔外科クリニック 親知らず口腔外科担当
・医療法人社団和晃会クリーン歯科 分院長就任
・医療法人社団横浜駅前歯科矯正歯科 矯正口腔外科担当
・医療法人社団希翔会日比谷通りスクエア歯科