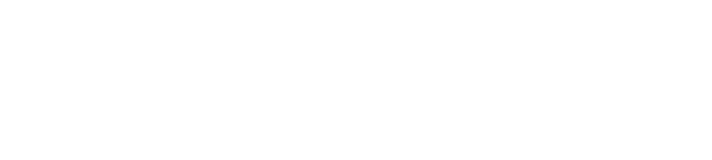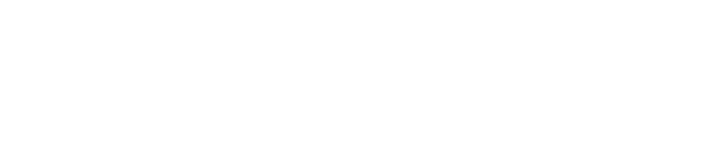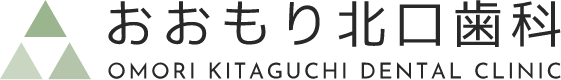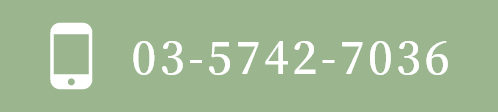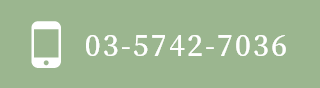症例紹介㉟親知らず抜歯(20代後半女性)
2025.04.30
症例紹介⑬表側ワイヤー矯正(20代後半男性)
2025.04.28
歯紅の原因とは?口紅が歯につく理由と簡単な対策法
2025.04.26
症例紹介㉞親知らず抜歯(20代後半女性)
2025.04.26
口内炎の種類と対処法を解説!正しいセルフケアとは
東京都大森駅徒歩50秒の歯医者・歯科「おおもり北口歯科」です。
口内炎ができると、食事も会話もつらく感じてしまい、日常生活の質が下がったと感じることはありませんか?
「繰り返す」「なかなか治らない」といった口内炎の悩みには、適切な知識と予防が欠かせません。
今回は、口内炎の症状や種類、そして具体的な予防法について解説します。
また、再発を防ぐために今すぐ取り入れられる生活習慣のポイントも丁寧にお伝えします。
読むことで、痛みの原因に納得し、再発を防ぐセルフケアまで身につけることができます。
結論として、口内炎は生活習慣の見直しと正しいケアでしっかり予防・改善できる疾患です。口内炎とはどのような症状か
口内炎とは、口の中の粘膜に炎症や潰瘍ができる状態を指します。
頬の内側、舌、唇の裏、歯ぐきなどに発症し、痛みやしみる感覚を伴うことが一般的です。
日常生活に大きな影響を与え、食事がしづらくなるだけでなく、会話や歯磨きすら億劫になるケースもあります。
免疫力が落ちているときにできやすく、繰り返しやすいのも特徴です。
特にストレスや疲労、栄養不足が関与しているとされ、口内炎は体調のバロメーターとも言えるでしょう。主な口内炎の種類と原因
口内炎には複数の種類があり、それぞれ原因や症状に違いがあります。
最もよく見られるのが「アフタ性口内炎」で、疲労やストレスが引き金になるケースが多く、円形の白い潰瘍が特徴です。
次に「外傷性口内炎」は、誤って頬を噛んだり、やけどをしたりした傷口から炎症が起こるタイプです。
さらに「ヘルペス性口内炎」はウイルス感染によるもので、発熱とともに水疱が現れます。
また「カンジダ性口内炎」は、口内の常在菌であるカンジダ菌が免疫低下によって異常繁殖し、白い膜状の炎症を引き起こします。以下のように原因別に分けられます。
- ・アフタ性口内炎:免疫力の低下、ビタミン不足、ストレスなど
- ・外傷性口内炎:物理的な刺激(噛み傷、入れ歯、やけどなど)
- ・ヘルペス性口内炎:単純ヘルペスウイルスの感染
- ・カンジダ性口内炎:常在菌の異常繁殖(ドライマウスや基礎疾患のある方に多い)
口内炎と見分けがつきにくい疾患
中には口内炎と似たような症状を示しながらも、より深刻な疾患が隠れている場合もあります。
代表的なものは「舌がん」や「白板症」です。
舌がんは舌の縁にできやすく、初期は痛みがほとんどないため見逃されやすいです。
白板症は前がん病変とも呼ばれ、口の粘膜に白い変化が見られ、こすっても剥がれないのが特徴です。
どちらも自然治癒することはありません。
2週間以上症状が続く、または大きくなる、繰り返し発症する場合は、速やかに歯科や口腔外科を受診しましょう。口内炎の対処法と治療の選択肢
口内炎ができてしまったら、痛みを和らげ早く治すためのケアが大切です。
症状に応じた市販薬を活用することも効果的です。
患部の状態により、パッチ・軟膏・内服薬などを使い分けましょう。
たとえば、潰瘍が一つだけであれば貼付薬、広範囲にできた場合は塗り薬が適しています。
また、炎症や細菌感染を防ぐために、うがいやトローチを併用するのもおすすめです。よく使われる市販薬の種類と特徴は以下の通りです。
- ・パッチタイプ:貼ることで物理的刺激を防ぎ、治癒を促進
- ・軟膏タイプ:凹凸のある場所にも使いやすく、保護作用あり
- ・内服薬:ビタミンB群などを補給し、体の内側から修復をサポート
- ・トローチ・うがい薬:殺菌作用により口腔内を清潔に保つ
口内炎を防ぐための具体的な生活習慣
口内炎の予防には、日頃の生活習慣を見直すことが最も重要です。
まず、栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠を意識しましょう。
特にビタミンB群やC、Aを積極的に摂取することで、粘膜の健康を保つ助けになります。
また、ストレスを抱え込まず、こまめなリフレッシュを意識することもポイントです。
加えて、口の中を常に清潔に保ち、乾燥を防ぐことで口内環境が整います。予防に役立つ生活習慣は次の通りです。
- ・食事はビタミンB群・C・Aを意識して摂る
- ・十分な睡眠で体の回復を促す
- ・歯磨きやうがいで口腔内を清潔に保つ
- ・入れ歯や矯正器具は清潔を保ち、違和感があれば調整を受ける
- ・唾液の分泌を促すためによく噛んで食べる、水分補給も忘れずに
まとめ
口内炎は身近なトラブルですが、放置すると治りにくくなり、QOLの低下を招きます。
主な原因は免疫力の低下や口腔内の不衛生などであり、種類ごとに症状や対処法も異なります。
日々のセルフケアと生活習慣の見直しで、多くの口内炎は予防可能です。
繰り返す場合や症状が重い場合は、迷わず専門医を受診することが早期回復の近道です。少しでもお役に立てれば幸いです。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。監修者
神奈川歯科大学卒業後、中沢歯科医院 訪問歯科治療担当
医療法人社団葵実会青葉歯科医院 分院長就任
シンタニ銀座歯科口腔外科クリニック 親知らず口腔外科担当
医療法人社団和晃会クリーン歯科 分院長就任
医療法人社団横浜駅前歯科矯正歯科 矯正口腔外科担当
医療法人社団希翔会日比谷通りスクエア歯科
おおもり北口歯科 開業
昭和大学口腔外科退局後は、昭和大学歯学部学生口腔外科実習指導担当経験 また、都内、神奈川県内の各歯科医院にて出張手術担当。
【所属】
・日本口腔外科学会
・ICOI国際インプラント学会
・日本口腔インプラント学会
・顎顔面インプラント学会
・顎咬合学会
・スポーツ歯科学会
・アメリカ心臓協会AHA
・スタディーグループFTP主宰【略歴】
・神奈川歯科大学 卒業
・中沢歯科医院 訪問歯科治療担当
・医療法人社団葵実会青葉歯科医院 分院長就任
・シンタニ銀座歯科口腔外科クリニック 親知らず口腔外科担当
・医療法人社団和晃会クリーン歯科 分院長就任
・医療法人社団横浜駅前歯科矯正歯科 矯正口腔外科担当
・医療法人社団希翔会日比谷通りスクエア歯科
- HOME
- ブログ
2025.04.19
3Shape社が来院!意見交換で得た新たな学び

見学&意見交換で得られた気づき

日本での使用方法はどのようにしているかなど、現状の問題点や解決方法、今後臨床の現場において望むことは何かなど、幅広い意見交換を行いました。
現場レベルでの新たな使用方法などもお伺いし、患者さんたちにもっともっと有益な使い方を習得させていただきました。
意見交換の他に当院の見学も行ってもらい、当院の設備やスキャンの使用頻度回数、当院のスタッフの技術レベルをとても喜んでもらえてたのは、我々も大変な自信になりました。

今後も口腔内スキャンを望む全ての患者様たちのために我々は日々アップデートを続け、高レベルな治療を継続し、またお会いできるように精進いたします。
執筆者
神奈川歯科大学卒業後、中沢歯科医院 訪問歯科治療担当
医療法人社団葵実会青葉歯科医院 分院長就任
シンタニ銀座歯科口腔外科クリニック 親知らず口腔外科担当
医療法人社団和晃会クリーン歯科 分院長就任
医療法人社団横浜駅前歯科矯正歯科 矯正口腔外科担当
医療法人社団希翔会日比谷通りスクエア歯科
おおもり北口歯科 開業
昭和大学口腔外科退局後は、昭和大学歯学部学生口腔外科実習指導担当経験 また、都内、神奈川県内の各歯科医院にて出張手術担当。
【所属】
・日本口腔外科学会
・ICOI国際インプラント学会
・日本口腔インプラント学会
・顎顔面インプラント学会
・顎咬合学会
・スポーツ歯科学会
・アメリカ心臓協会AHA
・スタディーグループFTP主宰
【略歴】
・神奈川歯科大学 卒業
・昭和大学口腔外科口座
・中沢歯科医院 訪問歯科治療担当
・医療法人社団葵実会青葉歯科医院 分院長就任
・シンタニ銀座歯科口腔外科クリニック 親知らず口腔外科担当
・医療法人社団和晃会クリーン歯科 分院長就任
・医療法人社団横浜駅前歯科矯正歯科 矯正口腔外科担当
・医療法人社団希翔会日比谷通りスクエア歯科
・おおもり北口歯科 開業
東京都大森駅からすぐ近くの歯医者・歯科
『おおもり北口歯科』
住所:東京都大田区山王2丁目5−2 福島屋ビル 1F
TEL:03-5742-7036
2025.04.18
症例紹介㉝親知らず抜歯(20代前半女性)
2025.04.16
院内勉強会の様子
目次
おおもり北口歯科の院内勉強会とは

我々おおもり北口歯科では、歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、受付の全スタッフが集合し、毎月末、院内勉強会を行っております。
普段は最新の歯科治療方法や治療器具の操作説明実習、患者さんたちへの治療計画作成、各種改善項目を全員で勉強しております。
3月の勉強会

3月に行った院内勉強会では、大阪の長谷先生をお招きして口腔内写真9枚法の撮影方法を強化していただきました。
また新型の一眼レフカメラを導入し、これにより更にスムーズに更に精度を高くし、出来るだけ患者様の負担にならずより感動してもらえる写真撮影が可能になりました。
当院では撮影する全員がとても熱心に練習してくれております。
この9枚法の撮影は当院では「3分以内に撮影出来なければ、患者さんの撮影は出来ない」という厳しい試験目標としていますが、間もなく全員突破できるはずです。
患者様に伝わる写真と検査の在り方
当院では4月から検査方法を更に強化し、より患者さんたちに自分の口腔内に興味や理解をもっていただくことを目的にこの口腔内9枚法も積極的に取り入れていきます。
歯医者に来ただけなのに、写真なんていらないでしょと言われることもまだまだたくさんありますが、撮影する理由や目的もしっかりご説明させていただき、治療の効果を最大限ご理解してもらえるように、そして来てよかった、治療してよかったと感じてもらえるようにスタッフ一同鋭意努力していきます。



執筆者
神奈川歯科大学卒業後、中沢歯科医院 訪問歯科治療担当
医療法人社団葵実会青葉歯科医院 分院長就任
シンタニ銀座歯科口腔外科クリニック 親知らず口腔外科担当
医療法人社団和晃会クリーン歯科 分院長就任
医療法人社団横浜駅前歯科矯正歯科 矯正口腔外科担当
医療法人社団希翔会日比谷通りスクエア歯科
おおもり北口歯科 開業
昭和大学口腔外科退局後は、昭和大学歯学部学生口腔外科実習指導担当経験 また、都内、神奈川県内の各歯科医院にて出張手術担当。
【所属】
・日本口腔外科学会
・ICOI国際インプラント学会
・日本口腔インプラント学会
・顎顔面インプラント学会
・顎咬合学会
・スポーツ歯科学会
・アメリカ心臓協会AHA
・スタディーグループFTP主宰
【略歴】
・神奈川歯科大学 卒業
・昭和大学口腔外科口座
・中沢歯科医院 訪問歯科治療担当
・医療法人社団葵実会青葉歯科医院 分院長就任
・シンタニ銀座歯科口腔外科クリニック 親知らず口腔外科担当
・医療法人社団和晃会クリーン歯科 分院長就任
・医療法人社団横浜駅前歯科矯正歯科 矯正口腔外科担当
・医療法人社団希翔会日比谷通りスクエア歯科
・おおもり北口歯科 開業
東京都大森駅からすぐ近くの歯医者・歯科
『おおもり北口歯科』
住所:東京都大田区山王2丁目5−2 福島屋ビル 1F
TEL:03-5742-7036
2025.04.15
症例紹介㉜親知らず抜歯(20代前半女性)
2025.04.14
症例紹介⑭GBT(Guided Biofilm Therapy)20代後半男性
2025.04.12